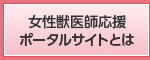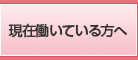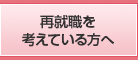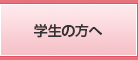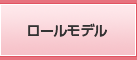獣医師生涯研修事業Q&A 小動物編(日本獣医師会雑誌 第74巻(令和3年)第2号掲載)
症例:犬,12歳,避妊雌,パグ
既往歴:特になし
近医における主訴:慢性的な下痢があったが特に治療を行っていなかった.しかし最近血便を認め,数日前から元気及び食欲の低下を認めた.
近医における検査所見:血液検査では再生不良性貧血,白血球数の増加,低アルブミンを認める.エコー検査では消化管の層構造が破綻した腫瘤形成を認める.
近医における診断:腸腺癌もしくは肉腫
治療経過:対症療法として皮下点滴,エンロフロキサシン皮下投与,プレドニゾロン皮下投与を2 日間実施した後紹介来院
〔当院での検査所見〕
一般状態:下痢と嘔吐は改善し食欲も回復
血液検査:表のとおり
超音波検査:消化管(主に小腸領域)に層構造が破綻した複数の腫瘤と小腸全域に粘膜の肥厚(約5mm)を認める(図1a,b).
細胞診:腫瘤及び粘膜肥厚部より得られた材料では好酸球の集簇を認め,明らかな腫瘍性疾患を示唆する所見は認められなかった.
質問1:近医初診時に疑うべき疾患は何か
質問2:初診時近医で行った治療の中でその後の診断及び治療を妨げる可能性があるものはどれか
質問3:細胞診の結果より次に行うべき診断法は何か
解答と解説
質問1に対する解答と解説:
慢性的な下痢及び嘔吐そして食欲不振は臨床現場でしばしば遭遇する症状である.これらの原因としては異物による消化管の閉塞や炎症性腸疾患,そして腫瘍性疾患が考えられる.本症例は慢性経過を辿っており,また消化管に腫瘤が確認され,さらに中高齢であることから腫瘍性疾患と考えるのが妥当であろう.消化管に発生する腫瘍としては腸腺癌,線維肉腫や消化管間質腫瘍(Gastrointestinal StromalTumor)などが挙げられるが,消化器型リンパ腫である可能性も忘れてはならない.消化器型リンパ腫は犬及び猫でしばしば認められる腫瘍であり,慢性的な下痢,嘔吐,貧血そして低アルブミンを認める.また,白血球数の増加については残念ながら初診時の内訳を知ることはできなかったが,末梢血中に腫瘍細胞が出現していた可能性を考慮するべきであっただろう.
質問2に対する解答と解説:
プレドニゾロンなどの副腎皮質ホルモン剤は臨床現場で頻用される薬剤である.副腎皮質ホルモンはリンパ球に対してApoptosis を誘起することが知られ,このことから,リンパ腫の化学療法プロトコールに組み込まれている.しかし本症例においては腫瘤性病変が認められていたにもかかわらず,炎症性腸疾患の治療が行われており,プレドニゾロンが投与されていた.副腎皮質ホルモンのリンパ腫に対する抗腫瘍効果が得られ,一時的に症状は改善したものの,これにより後の診断及び治療がより困難となる.
実際に本症例においてエコーガイド下で複数箇所を複数回にわたってFNA を行い,腸管の腫瘤及び腸管壁の肥厚部より得た材料の細胞診を行った(図2).
塗抹標本上ではリンパ球の残骸と思われるApoptosis小体(白円内)が確認されたのみで,明らかなリンパ腫を示唆する大型リンパ球の単一増殖所見は認められず,正常なリンパ球のみが認められた(白矢頭).しかし標本上では好酸球の集簇(黒矢頭)が確認されたことより,やはりリンパ腫であることを疑わざるをえなかった.
消化管における好酸球の集簇は,好酸球性腸炎のみならず肥満細胞腫においても認められ,またリンパ腫でも生じることが知られる.これはリンパ腫の細胞が産生するサイトカインによって好酸球が局所に集簇した結果とされている.このため,本症例では本来であればFNA により得られた細胞標本にてリンパ腫の診断が下り,速やかにリンパ腫の化学療法へと移行できた可能性があったにもかかわらず,副腎皮質ホルモンの投与により細胞診での診断を行うことができなかった.またリンパ腫であった場合には,副腎皮質ホルモン単独での先行治療ではその投与期間に関わらず,後に続く化学療法の寛解期間を短縮させる可能性がある.このことからも,消化管のみならず種々のタイプのリンパ腫において副腎皮質ホルモンのみ先行投与することは,特に診断が下る前には避けるべきである.
質問3に対する解答と解説:
消化管の正常な層構造が破綻している場合には腫瘍性疾患である可能性が高いため,超音波ガイド下での生検が診断やステージの把握に有効となる.しかし,本症例では質問2 で述べたようにFNA では診断に足る十分な材料が得られず,リンパ腫を疑いながらも化学療法を始めることができなかった.上部消化管であれば内視鏡生検による診断の可能性も考慮するべきであるが,本症例では腫瘤が空回腸に存在し,内視鏡での生検は困難と考えられた.また,注意するべきは内視鏡生検では粘膜下組織までの十分な診断の根拠となる材料が得られない可能性がある.このため,やはり試験的開腹により腸管の全層生検を行うのが最も確実な方法といえる.本症例でも飼い主と相談し,麻酔などのリスクを十分に説明したうえで試験開腹による生検を行った.
以下に手術所見を示す.
当初は開腹し,消化管の一部を腹腔外に牽引してトレパンによる全層生検を行う予定であったが,空回腸全域に結節状の病変が広がっており,また,複数箇所で穿孔が認められた(図3a).このため,結節状の病変部と穿孔が疑われる領域(空腸の一部及び回腸全域)の切除を行い,病理組織診断に提出した(図3b).病理組織診断結果はT 細胞性リンパ腫であり,この結果から輸血を行い,速やかに化学療法(L-CHOP)を開始した.術後約5 週間にわたって部分的な寛解を得られたが,その後下痢及び嘔吐が再発し,当院初診時より56 日後に死亡した.
臨床現場でさまざまなタイプのリンパ腫に遭遇する機会は少なくなく,特に本症例のような消化器型T 細胞性リンパ腫は予後が悪いため迅速に診断し,化学療法を開始する必要がある.しかし,漫然とした治療や検査などによりその診断や治療が遅れると,不幸な結果が予想しないほどのスピードでやってくる.リンパ腫についての化学療法の情報は文献などに溢れており,その中から何を選択するかは飼い主の事情や獣医師の経験などによってさまざまであろう.しかしリンパ腫の診断には選択肢はなく,細胞診もしくは組織診によるところであり,細胞診で明らかな診断が得られなければ,たとえ侵襲が高いとしても組織診断を行うことを躊躇してはならない.初期対応の誤りはその後の診断や治療を複雑かつ困難にすることを再認識していただければと思う.
キーワード: 消化管腫瘍,リンパ腫,副腎皮質ホルモン,Apoptosis,好酸球