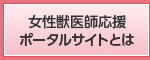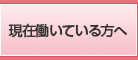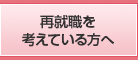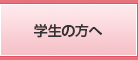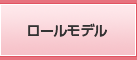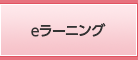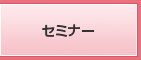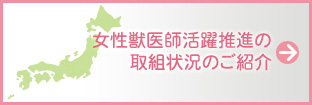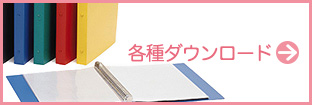獣医師生涯研修事業Q&A 小動物編(日本獣医師会雑誌 第78巻(令和7年)第1号掲載)
症例:Mix 猫,去勢雄,13 歳
主訴:1 カ月前から声が出なくなり,食欲廃絶,呼吸促拍.抗菌薬の効果は認められないが,プレドニゾロン0.9 mg/kg SID により症状が少し改善していた.
身体検査:体重4.7 kg,体温38.2℃,心拍数180 回/ 分,呼吸数50 回/ 分,呼吸様式は腹式及び努力性であり,開口呼吸.
無麻酔下CT 検査(図1):輪状・甲状軟骨・気管輪の全周性の肥厚による内腔の狭窄(矢印)が認められた.
処置:採材による確定診断は危険と判断しメチルプレドニゾロン酢酸エステル注射液5 mg/kg を1 度のみ皮下注射し経過観察とした.
経過:投与後1 週間の時点で病変はCT 上完全に消失し,呼吸促拍を含めた臨床症状も改善した.無治療で経過は良好だったが7 カ月後に吐血を認め来院した.
無麻酔下CT 検査(7 カ月後):喉頭及び気管腫瘍の再発なし.
血液検査(7 カ月後):非再生性貧血(PCV 18%),血小板減少症(128×103/μl),高蛋白血症(>12.0 g/dl)及び高グロブリ尿検査:尿蛋白/ クレアチニンは3.06と高値を認めた.
超音波検査:脾臓にてび漫性に低エコー源性の結節が認められた.腹腔内リンパ節は多数腫脹し,幽門部にて筋層の肥厚も認めた.
細胞診(脾臓,図2):図に示すように,血液成分を背景に多数の円形から楕円形の独立円形細胞が採取された.細胞の大きさは好中球と比較し2 倍以上大きく,核は偏在し2 ~ 3 核の複数核を保有する細胞も見られた.細胞質は広く核周囲に明庭も認められた.
血清蛋白分画電気泳動(図3):図に示すようなγグロブリン分画の顕著な上昇(モノクローナルガンモパチー)を認めた.
質問1:疑われる疾患は何か.
質問2:有効な治療法は何か.
解答と解説
質問1に対する解答と解説:
本症例では,メチルプレドニゾロン酢酸エステル注射液により気管腫瘤が消失したため,確定診断をつけることができず経過観察していた.7 カ月後の再診時では気管腫瘍は消失したままだったが,腹腔内臓器へ転移が認められていた.このような,ステロイドに一時的にかつ良好に反応する腫瘍の鑑別として,リンパ腫,形質細胞腫,肥満細胞腫などが考えられる.追加検査にて明らかになったモノクローナルガンモパチーは,B 細胞性リンパ腫でも認められるが,脾臓の細胞診にて形質細胞腫に特徴的な所見(核の多型性,偏在かつ車軸状の核と核周明庭を持つ特徴的な細胞の腫瘍増殖)が見られた.このことから,本症例を気管原発の髄外性形質細胞腫及び腹部臓器への転移と診断した.高グロブリン血症は気管腫瘍があった際にも存在していた可能性があるが,プレドニゾロンにより治療されていたため,マスキングされていたと考えられる.また,非再生性貧血及び血小板減少の原因は形質細胞腫の骨髄浸潤の可能性も考えられるが,血液塗抹中には形質細胞は見られず,頻回の吐血による影響が強いと判断した.
猫の形質細胞腫は猫の形質細胞腫関連疾患FelineMyeloma Related Disorders(FMRD)と呼ばれ,以下に分類される.
- ① 骨髄腫
- ② 皮膚の髄外性形質細胞腫
- ③ 皮膚以外の髄外性形質細胞腫
- ④ 骨の孤立性形質細胞腫
- ⑤ IgM マクログロブリン血症
- ⑥ 免疫グロブリン産生性リンパ腫
- ⑦ 形質細胞性白血
本症例では③と診断したが,確定診断には形質細胞の腫瘍増殖の確認,モノクローナルガンモパチーの確認以外に,尿中に排出されるベンス・ジョーンズ蛋白の検出や免疫組織化学染色にて形質細胞マーカーMUM1 が陽性であることなどが挙げられる.本症例では蛋白尿は出ていたがベンス・ジョーンズ蛋白尿は陰性だった.この理由として,ベンス・ジョーンズ蛋白の検出感度は猫では59%程と高くないことが考えられる.また,X 線検査での骨パンチアウト像(骨融解像)が見られることもあるが,猫ではきわめてまれである.診断材料が少ない場合,組織検査により確定診断がつくが,本症例のように病変が腹腔内臓器のみであり,状態も悪い症例では生検は困難であり,やむを得ず早期に治療介入する場合もある.
質問2に対する解答と解説:
犬の多発性骨髄腫の場合では,メルファラン・プレドニゾロン療法(MP療法)が最も治療データが多く有効とされている[1].孤立性の髄外性形質細胞腫の場合は外科的あるいは放射線治療が有効であり,状況により使い分けや組み合わせることが必要である.一方,FMRD の場合では,孤立性の場合は局所療法が有効なのは同じだが,骨髄腫や複数臓器へ転移している髄外性形質細胞腫の場合では,メルファランにより強い骨髄抑制が出るため,注意が必要である.猫の骨髄腫に対するMP療法の効果はいくつかの症例で報告されており,半年以上の生存期間が得られる症例もいる[2, 3].しかし,反応しても生存期間が数週間程度の症例も存在しているため,現状の治療のみでは制御できない症例も多い. その他に治療として用いられているのはCHOP 療法やニムスチンだが,いずれもまだデータが乏しい.近年では,プロテアソーム阻害剤であるボルテゾミブによる治療が有効であることも確認されており[4],今後のデータの蓄積が期待される.
参考文献
- [ 1 ] Fernández R, Chon E : Comparison of two melphalan protocols and evaluation of outcome and prognostic factors in multiple myeloma in dogs, J Vet Intern Med, 32, 1060-1069 (2018)
- [ 2 ] Hanna F : Multiple myelomas in cats, J Feline Med Surg, 7, 275-287 (2005)
- [ 3 ] Patel RT, Caceres A, French AF, McManus PM :Multiple myeloma in 16 cats: a retrospective study, Vet Clin Pathol, 34, 341-352 (2005)
- [ 4 ] Tani H, Miyamoto R, Miyazaki T, Oniki S, Tamura K, Bonkobara M, A feline case of multiple myelomat reated with bor tezomib, BMS Vet Res, 18:384 (2022)
キーワード:猫,髄外性形質細胞腫,FMRD,メルファラン,ボルテゾミブ