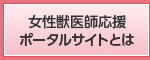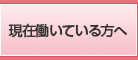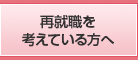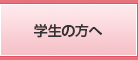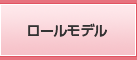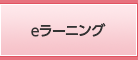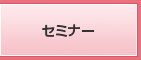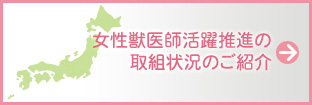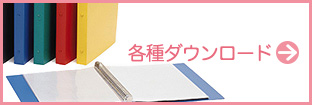獣医師生涯研修事業Q&A 小動物編(日本獣医師会雑誌 第78巻(令和7年)第10号掲載)
症例:10 歳10 カ月齢,ゴールデン・レトリバー,避妊済み雌
主訴:四肢起立困難
病歴:3 週間前から立ち上がるのに時間がかかるようになった.立ち上がったあとはスムーズに歩行できていた.症状は徐々に進行し,10 日前から家の中ではほとんど歩行しなくなった.ホームドクターを受診したところ,院内での歩行は可能であったが,歩行時に四肢のふらつきを認めた.ホームドクターで実施した胸部,腹部及び関節のX 線検査では異常は認められなかった.
消化器症状や呼吸器症状,排泄の異常等は認めておらず,食欲や飲水についても問題はない.
身体検査:体重26.5 kg.体温39.2℃.心拍数126 回/分.呼吸数30 回/ 分
神経学的検査:
意識状態:清明
知性・行動:特記事項なし
姿勢・歩様:院内では歩行可能
歩行は緩慢ではあるが,不全麻痺や運動失調は認めない.
姿勢反応:四肢で特記事項なし
脊髄反射:四肢で特記事項なし
脳神経検査:特記事項なし
傍脊柱における知覚過敏:なし
血液検査・血液生化学検査:CRP 及びWBCの高値を認めた.また,TP,ALP 及びT-Cho も高値であった.
質問1:疑われる病変部位はどこか.また,その中で最も疑わしい病変部位はどこか.
質問2:鑑別診断を進めるために追加すべき検査は何か.
解答
質問 1 に対する解答と解説:
正解:最も疑わしい病変部位:四肢の関節
主訴である“肢のふらつき”からは,運動器(神経,骨・関節,靭帯,筋)における異常,もしくは重度の内科疾患による全身状態の悪化を疑う.
四肢のふらつき以外の症状はないことから,運動器における異常の可能性が高いと考えられる.単肢ではなく四肢に異常が出ていることから,骨や靭帯の異常である可能性は低い.また,筋疾患の多くで筋マーカーであるCPKが高値となるが,本症例では基準値範囲内であったことから,筋疾患の可能性も低いと考えられる.
したがって,本症例では神経及び関節の疾患を疑う.神経疾患だった場合には,病変部位として脳,C1-T2 脊髄分節,末梢神経障害の可能性があげられる.神経筋接合部疾患の場合は運動不耐性を主徴とするため,本症例の臨床症状とは異なる.
本症例は神経学的検査で異常を認めておらず,神経疾患以外の可能性を十分考慮する必要がある.動き出しに症状が出やすいとのことであるが,神経疾患の場合,その症状は運動後に悪化することが多い.一方で,関節疾患の場合には動き出しの際に症状が出ることが多い.したがって,臨床症状及び神経学的検査の結果から,神経疾患よりも関節疾患の可能性が高いと考えられる.
血液検査では炎症マーカーであるCRP 及びWBCが顕著に高値を示していた.神経疾患で炎症マーカーが高値となる疾患は稀であり,代表例としてステロイド反応性髄膜炎・動脈炎が挙げられる.この疾患では頸部痛を主徴とするが,本症例では頸部痛は認めていない.一方で,関節疾患である多発性関節炎は,罹患すると四肢のふらつきを呈し,CRP が顕著に高値を示すのが特徴である.院内では歩行可能にも関わらず,家では動きたがらないという様子から,関節痛の存在により立ち上がりづらくなった可能性が考えられる.
以上から,本症例は多発性関節疾患に罹患している可能性を最も強く疑う.
質問 2 に対する解答と解説:
正解:関節液検査,必要に応じてMRI 検査,脳脊髄液検査及び電気生理学的検査
多発性関節疾患に罹患している可能性があることから,関節液検査を検討する.また,鑑別疾患として,脳及びC1-T2 脊髄分節の異常が疑われることから,MRI 検査及び脳脊髄液検査の実施も選択肢の一つとなる.末梢神経障害を疑う場合には,末梢神経機能の評価のために電気生理学的検査(誘発電位検査)の実施を検討する必要があるが,特殊な検査機器を必要とするため,一部の診療施設でのみ実施可能である.
本症例は,ホームドクターで神経疾患を疑って紹介されており,飼い主がMRI 検査を実施したいとの希望を持っていたため,関節液検査及びMRI 検査を実施した.MRI 検査では頭部及びC1-T2 脊髄分節には異常を認めなかった.関節液の評価のため,両側膝関節,両側手根関節の4 カ所から関節液を採取したところ,いずれの部位の関節液も粘稠度が低下しており,細胞診にて好中球を主体とした炎症細胞を多く認めた.この結果から,多発性関節炎により歩様異常が生じていると結論づけた.
多発性関節炎を起こす原因としては,反応性多発性関節炎(感染や消化管疾患,腫瘍に続発するタイプ)と,特発性免疫介在性多発性関節炎があげられる.本症例は高齢であることを考慮し,全身をCTにて評価したところ,腹腔内に腫瘍性病変を認めたことから,腫瘍に続発する多発性関節炎の可能性があると考えられた.反応性多発性関節炎でも免疫抑制療法に反応するとされていることから[1],腫瘍の精査及び治療と並行し,免疫抑制量のプレドニゾロンによる治療を提案した.飼い主はプレドニゾロン2 mg/kg で症状が寛解したため,腫瘍に対する精査及び治療を希望されなかった.したがって,本症例では腫瘍性疾患が反応性多発性関節炎を引き起こしたかどうかを確定することはできなかった.
本症例のように四肢のふらつき及び歩行困難が主訴のケースでは,神経疾患を疑うことが多いと思われるが,関節疾患の可能性も十分に考慮する必要がある.関節疾患と神経疾患の鑑別には神経学的検査が重要である.時に血液検査における炎症マーカーが診断の一助になることがある.また,多発性関節炎を疑う症例に対しては,基礎疾患の有無を評価すべきであると考えられる.
参考文献
- [ 1 ]Hagelskamp A, White AG, Gallman J, Starbird C, Neto RLALT : Pancreatitis, panniculitis, and polyarthritis syndrome in a dog with hyalinizing pancreatic adenocarcinoma, J Vet Diagn Invest, 36, 886-890 (2024)
キーワード:犬,多発性関節炎,CPR,炎症,ステロイド反応性髄膜炎・動脈炎