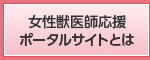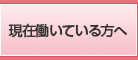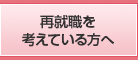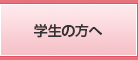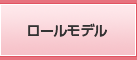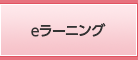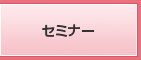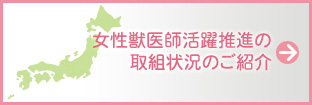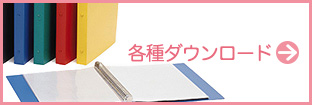獣医師生涯研修事業Q&A 公衆衛生編(日本獣医師会雑誌 第78巻(令和7年)第7号掲載)
獣医学教育モデル・コア・カリキュラム獣医公衆衛生学の1 科目である環境衛生学では,人や動物の健康にとってより良い環境を維持し,地球環境の保全に貢献するための基礎知識や関連法規を学びます.地球環境の保全においては,生物多様性の概念は重要なテーマです.一般的に,生物多様性の概念は「遺伝子の多様性」,「種の多様性」,「生態系の多様性」の3 つのレベルで捉えられます.生物多様性の保全に関する国内法の一つに,特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)があります.今回は,外来生物法に関連した問題を取り上げます.
質問1:外来生物法における「特定外来生物」の選定基準に該当しないものはどれか.
- a.海外起源である.
- b.おおむね明治以降に導入された.
- c.生態系への重大な被害がある.
- d.生きている個体だけでなく卵・種子も含まれる.
- e.家畜の伝染性疾病に係る重大な被害がある.
質問2:外来生物法における「特定外来生物」に該当しない動物はどれか.
- a.アライグマ
- b.ヌートリア
- c.カミツキガメ
- d.ノヤギ
- e.キョン
質問3:外来生物法において,「条件付特定外来生物」と「許可が不要な行為」の正しい組み合わせはどれか.
- a.クリハラリス(タイワンリス)─ 少数の相手への無償での譲渡・譲受
- b.ハクビシン ─ 野外での捕獲
- c.アメリカザリガニ ─ ペットとしての飼養
- d.ブルーギル ─ 販売目的での輸入
- e.アカミミガメ ─ 飼養個体の野外への放出
解答と解説
外来生物法(2005 年6 月施行)は,特定外来生物による生態系,人の生命・身体,農林水産業への被害を防止し,生物の多様性の確保,人の生命・身体の保護,農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて,国民生活の安定向上に資することを目的としています.日本の生物多様性を脅かす外来生物への対策に関するわが国初の法律です.外来生物法では,問題を引き起こす外来生物を特定外来生物として指定し,その飼養,栽培,保管,運搬,輸入といった取扱いを規制し,特定外来生物の防除等を行うこととしています.2024 年7 月1 日までに,哺乳類25 種類,鳥類7 種類,爬虫類22 種類,両生類18 種類,魚類26 種類など,合計162 種類の動植物が,特定外来生物に指定されています.しかし,外来生物法では,国内由来の外来生物(北海道のカブトムシや屋久島のタヌキなど)や明治時代よりも前に国内に導入された侵略的な外来生物(ノネコやノヤギなど)は特定外来生物の選定対象外となっているなどの課題も指摘されています.
外来生物にはペットなどの飼育由来のものが少なくありません.わが国では,エキゾチックアニマルの人気は高く,飼育者も増えています.飼育由来の新たな外来生物問題を防止するためには,ペットの適正飼育と終生飼養に関する獣医師による普及・啓発は不可欠です.
質問1に対する解答と解説:
正解:e
特定外来生物の選定は,「特定外来生物被害防止基本方針」(2014 年)に基づいて行われています.選定の基本的な前提として,①おおむね明治元年以降に日本に導入された生物であること,②個体としての識別が容易な大きさ・形態を有していること(菌類,細菌類,ウイルス等の微生物は対象外),③他法令上の措置によって外来生物法と同等程度の輸入・飼養等の規制がなされている外来生物は選定の対象としないこと,などとされています.これらの選定基準を満たす外来生物のうち,「生態系,人の生命または身体,農林水産業に係る被害」の状況を検討して特定外来生物が指定されています.なお,「農林水産業に係る被害」には家畜の伝染性疾病などに係る被害は含まないとしています.
選択肢のうち,「海外起源である」,「おおむね明治以降に導入された」,「生態系への重大な被害がある」,「生きている個体だけでなく卵・種子も含まれる」,はいずれも特定外来生物の選定基準に含まれます.「家畜の伝染性疾病に係る重大な被害」への対策は家畜伝染病予防法や植物防疫法などの他法令で措置されているため,外来生物法における農林水産業に係る被害には含まれません.
参考:「特定外来生物被害防止基本方針」(環境省・農林水産省,2022 年9 月)
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/files/kihon_rev_all_r4.pdf
(2025 年5 月9 日最終確認)
質問2に対する解答と解説:
正解:d
アライグマ,ヌートリア,カミツキガメ,キョンはいずれも特定外来生物に指定されています.アライグマはほぼ全国で,ヌートリアは主に西日本で,カミツキガメは千葉県や静岡県などで,キョンは千葉県や伊豆などで定着が確認されています.ノヤギは,家畜由来の外来生物ではありますが,明治以前に日本に導入されたことなどから,特定外来生物には指定されていません.しかし,小笠原諸島や八丈島,奄美群島などでは,高密度化したノヤギによる植生破壊や土壌流出により,陸域だけでなく海域の生態系への影響が深刻です.
質問3に対する解答と解説:
正解:c
外来生物法の改正法(2022 年5 月)で,通常の特定外来生物の規制の一部を当分の間,適用除外とする「条件付特定外来生物」を新たに指定できるようになりました.「条件付特定外来生物」は通称で,法律上は「特定外来生物」となります.2023 年6月から「条件付特定外来生物」の規制が開始されました.
2025 年4 月現在,アメリカザリガニとアカミミガメの二種が「条件付特定外来生物」に指定されています.これら二種では,通常の特定外来生物としての規制のうち,「一般家庭でのペットとしての飼養」,「野外での捕獲」,「少数の相手への無償での譲渡・譲受」は手続き不要(適用除外)になっています.しかし,「販売目的での輸入」や「飼養個体の野外への放出」,「野外で捕獲した個体を運搬して放出すること」は,通常の特定外来生物と同様に規制(禁止)されています.なお,選択肢のうち,クリハラリス(タイワンリス)とブルーギルは,通常の特定外来生物です.ハクビシンも外来生物ではありますが,特定外来生物には指定されていません.
アメリカザリガニとアカミミガメは,飼育者がとても多く,単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると,手続きが面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えると予想され,かえって生態系等への被害を生じるおそれがあります.そのため,現在飼育している個体はこれまで通り手続き不要で飼い続けることができるなど,一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物」に指定されました.
今後も,新たに「条件付特定外来生物」に指定される種が増えることが予想されますが,適用除外とする規制の内容は,種ごとに指定されることになっています.
参考:「条件付特定外来生物」に関する環境省Web サイトURL
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html#03
(2025 年5 月9 日最終確認)
キーワード:外来生物法,特定外来生物,条件付特定外来生物,生物多様性